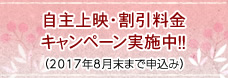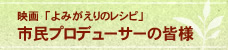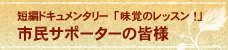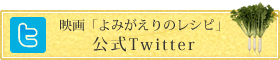推薦の言葉
『よみがえりのレシピ』を推薦します
太下義之(三菱UFJ リサーチ&コンサルティング 芸術・文化政策センター長)
本作品の監督・渡辺智史氏は、作品中にもその風景や市民たちが頻出する山形県鶴岡市の出身である。同氏は本作品の撮影時にまだ20歳代であった若手(1981年生)の映画監督であり、本作品はドキュメンタリー映画『湯の里ひじおり~学校のある最後の1年~』に続く監督第2作である。
そして本作品は、渡辺監督の出身地である山形県、とりわけ庄内地方を中心とする「在来作物」を題材としたドキュメンタリー映画である。「在来作物」とは、その土地で長年栽培され、人々に親しまれてきた野菜、果樹、穀類などの作物であり、長い間人々の生活を支え、地域独特の文化を継承する一翼を担ってきた。
ところでドキュメンタリー映画というと、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したマイケル・ムーア監督『ボウリング・フォー・コロンバイン』(2002年)のように、監督本人が取材対象に突撃インタビューするスタイルのプロパガンダ的な作品をイメージするかもしれないが、本作品で渡辺監督自身が声高な主張を行っているわけではない。
四季折々の美しい光景や瑞々しい在来作物の映像を背景に、農民たちは自らの想いを訥々と語り、在来作物を巡る科学的事実がテロップで淡々と流れていく。このように、扇情的に訴えかけるわけではなく、心地よい時が経過する中で、種を守り続け、次の世代に継承していくことの大切さが表現されている。
また、映像だけではなく、サウンドにおいても新しいタイプの「映画音楽」として意義深いチャレンジが行われている。初見では分かりにくいかもしれないが、本作品においては、現代作曲家の鈴木治行氏が単なる情緒に流れることの無い、映像と一体となった独特な音響空間を構築しているのである。
さて、本作品の題材となっている「在来作物」であるが、当地域の農家たちは自ら「在来作物」の種子を採取し、その中から種を選別することで結果として「育種」を行っている。そして、この「育種」を通じて、新たな系統も生み出されており、遺伝的多様性をもつ生物資源として、「在来作物」の保存・継承がなされてきた。
また、「在来作物」は、地域の栽培技術や食文化の継承を担う媒体としても貴重な文化財である。たとえば、焼畑農法は一部では環境破壊と誤解されることもあるようだが、むしろ、林業における伐採と植栽のサイクルに沿った持続可能な環境保全型の営みであり、「在来作物」であるカブの栽培を通じて、焼畑農法も継承されてきたのである。
本作品に繰り返し登場し、「在来作物」の意義を語る山形大学農学部准教授・江頭宏昌氏は、この「在来作物」の存在と意義を見つめ直すことを通して地域における食文化を再発掘することなどを目的として、研究者、農民、市民などで構成される「山形在来作物研究会」を10年ほど前に設立している。
さて、本作品に頻出するもう一人の人物は、レストラン「アル・ケッチァーノ」オーナー・シェフの奥田政行氏である。「アル・ケッチァーノ」は、在来野菜など旬の地元産こだわり食材を使い、生産者の顔の見えるメニューを提供しているイタリアン・レストランで、予約の取りにくいレストランとしても全国的に有名である。
本作品において、カブ農家・後藤氏が自分の育てたカブを奥田氏が調理した料理を味わった時の「何これ!これが俺のカブ?」というエピソードが紹介されるが、この発言に象徴されるように、料理とは素材(在来作物)に新しい命を吹き込む、極めてクリエイティブな行為であることを観客はあらためて認識することになる。
本作品を観て、認識を新たにする対象は料理だけではない。カブを栽培するおばあちゃんが、カブづくりを「何歳になってもやめられない」と発言しているように、農業に従事して、自分が育てた作物を他の人に食べてもらうことで、食べた人を幸せにするという喜びが画面から伝わってくる。実は農業もクリエイティブな産業であったのである。
農業に関しては昨今、“TPP(Trans-Pacific Partnership;環太平洋戦略的経済連携協定)”の話題で持ちきりであるが、TPPに対する「賛成/反対」という以前の問題として、私たちの暮らしの基盤となる食料を単なる“商品”として市場原理に晒してグローバルな取引をすることが本当に私たちの幸福につながるのか、という真摯な議論が必要であろう。
そして、当たり前のことではあるが、農業や農作物は農民だけが守るものではい。たとえば、地産池消のレストラン、研究者、地場の産業、学校での食育、家庭での世代を超えた教育など、示唆は本作品の中に散りばめられている。そして何よりも、消費者である私たち自身が変わっていかないと、大切なものを守る続けることはできないだろう。
その意味では、本作品が製作された仕組みは興味深い。市民有志が製作委員会を設立し、一口1万円で資金を寄付する「市民プロデューサー」たちによって本作品は実現したのである。すなわち、本作品のテーマ「在来作物とその種」と同様に、本作品自体が新しいドキュメンタリー作品の製作の可能性を模索する、新しい“種”となっているのである。
一期一会によって本作品の観客となった私たちは、美しい映像に身を委ねて楽しむだけでは、この作品の持つ価値に応えることにならない。まずは、自分たちの生活を支えている農業や自然への感謝と、自分たちの現在のライフスタイルに対する真摯な問いかけから始めていく必要があるだろう。